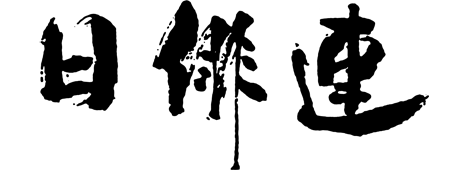新著作権法の草案発表
1966(昭和41)年4月、4年越しで続けられていた著作権制度審議会の審議が終わりました。1661(昭和36)年に採択、64年に発効した「ローマ条約(実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約)」を基礎に、1899(明治32)年来、60年以上も続いてきた旧著作権法を全面改正しようという考え方がいよいよまとまったのです。文部省文化局(文化庁はまだ設立されていませんでした)は、早速審議会の審議結果を踏まえて新著作権法の草案を、66年10月23日に発表しました。
そこで俳優は発言します。
「ネット料、リピート料が実演家に!」
「疑問を残すテレビ映画の扱い」
66年12月5日付けの放芸協機関誌「放送人」はこんな二つの見出しを立てて、新法草案の問題点を解説しています。何が問題だったのでしょうか。まず、新法草案の主要部分を抜粋してみましょう。草案にはこんな条文が並んでいます。
草案 第1条
「この法律は、著作者並びに実演家、レコード製作者及び放送事業者の権利について定め、公共の利益との調和を考慮して、これらの者の人格的又は経済的な利益の保護を図り、もって文化の向上発達に資することを目的とする」
草案 第2条第3項
「この法律において「映画の著作権」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ固定されている著作物を含み、もっぱら放送のための技術的手段として放送事業者によって作成されるものを含まないものとする」
草案 第2条第7項
「この法律において実演家とは、実演に準ずるもので芸能的な性質を有するものを含むものとする」
草案 第11条
「映画の著作物の著作者は、映画監督その他映画の著作物の全体的形成に創作的に関与したものとする」
草案 第31条
「映画の著作物の著作権は、映画製作者に帰属する」
草案 第95条第2項
「隣接権は映画の著作物には適用されない」
草案 第97条
「実演の放送について実演家の許諾を得た放送事業者は、その放送の実演が再放送された場合には、正当な額の報酬を当該実演に係る実演家に支払わなければならない(註「再放送」とは、放送事業者が他の放送事業者を通じて同時に放送すること、つまりネット)」
草案 第98条第3項
「放送事業者は、第1項の規定により作成した録音物又は録画物を実演家の許諾を得た放送以外の放送のために使用し、又は他の放送事業者の放送のために提供する場合には、正当な額の報酬を当該実演に係る実演家に支払わなければならない」
つまり、「ネット料」や再放送に関わる正当な額の報酬、すなわち「リピート料」が新設されることになって、実演家には新たな権利が認められることになったというわけです。「放送人」は、このことを新しい成果の一つとして評価しました。
しかし、評価できる部分がある一方で、実演家が「機械的失業」に追い込まれていく土壌が新法の成立過程で出来上がってきていました。言わずと知れた「映画」の特別扱いです。上記の草案の中で明らかなように、映画の著作物には隣接権は及ばないとか、本来は放送用に制作された放送物たるべきテレビドラマ等が、放送局以外の製作者によって作られたというだけで劇場用映画と同じ扱い、隣接権の対象外になってしまうという大きな矛盾点が抱え込まれたままになっていたのです。
テレビの放送番組に既存の劇場用映画が使われるようになれば、その分だけ実演家が直接出演するドラマの制作は行われないことになります。すなわち、実演家は出演する機会を失うことになり、その時間分失業したことになってしまいます。ましてや、俗に「放送局の下請会社」といわれる製作会社で作られたドラマが、「テレビ映画」との名前で呼ばれるが故に「映画扱い」となり、再放送されているのに二次使用料が支払われないとなったら、実演家は文字通り飯の食い上げ状態に追い込まれてしまうのです。放送技術が発達し、機械による製作がスムーズに行われるようになったがために生ずる実演家の失業、つまり「機械的失業」が切実な問題になるようになったのです。
問題点が浮き彫りにされるのに伴って、修正に向ける意見は当然強くなっていきます。俳優をはじめ、音楽家、舞踊家、演芸家等々、あらゆる分野の芸能実演家を組織する芸団協(日本芸能実演家団体協議会)では、本文143条、附則21条にのぼる草案がいよいよ国会に上程される見通しとなった1967(昭和42)年1月7日、文部大臣宛に長文の意見書を提出しました。とてもその全文を収録して紹介する紙幅はありませんが、要点を拾っておくと、
- 新法制定に当たって当局が「隣接権制度」を創設しようとする意図には賛意と敬意を表する。
- 劇場用映画と放送用映画のための固定物について、法文上明らかにしないと、後々混乱が生ずる恐れがある。
- 草案中の「実演家」の語は「芸能家」とする方が適当である。
- 草案第11条の中でわざわざ「映画監督その他」と監督だけを著作者として例示するのは無意味であり、この語は削除すべきである。
- 草案第31条については「映画の著作物の著作権は、特約がない限り映画製作者(映画の著作物の製作に発意と責任を有するものをいう)に譲渡されたものと推定する」と改められたい 。
- 「機械的失業」から芸能家を護るための法規定を希望する。
- 放送用の固定物が放送業者によって永久に保存されると、「機械的失業」を助長し、実演芸術の進歩にブレーキをかける原因となる。従って保存期間には制限を加えるべきである。
- 次のような場合には、映画製作者は実演家に正当な報酬を支払わなければならないことを法律上規定するよう希望する。
(1)当該映画の最初の公表から10年経ってのち、これを再上映する場合
(2)当該映画の音声又は音声と影像が包装される場合
(3)当該映画が海外に輸出される場合、などとなっています。
さて、ここで問題にされるべきは、(5)で規定を希望している映画製作者への著作権の譲渡推定についてでしょう。映画に限らず視聴覚的実演の固定物に関する著作権をどこに帰属させるかについては、近年、WIPO(世界知的所有権機関)で新しい国際条約を作成する際にも大議論になったところです。1996(平成8)年12月の外交会議での議論の決裂からWIPOが常設委員会を通し、実に丸4年を費やして準備した原案にもかかわらず、「製作者への譲渡推定」は2000(平成12)年12月の外交会議でも合意されませんでした。「権利が譲渡されたと推定する」などという曖昧な表現では嫌だ、はっきり「譲渡する」と明言すべきであると主張する製作者(とくにアメリカ・ハリウッドの大映画資本)の意見と「そもそも製作者への権利譲渡などおかしい」とする意見とが対立したまま歩み寄りが見られなかったからです。
新しく著作権法を作り直そうとした1960年代後半の日本の場合も同じでした。芸団協からの意見書は取り上げられず、新法が制定されたときには「映画の著作物の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する」(第29条)となってしまったのです。このことが後々ずっと問題を抱え続けてきたことは、芸能実演家なら誰でもが実感してきたことでした。
映画の著作権帰属問題に限らず、文部省が当初示した新法の草案は、そのまま現行著作権法の条文として成立したわけではありません。むしろ、1971(昭和46)年1月1日に施行された新法の条文は、実演家にとって、はるかに厳しい内容を含んだものになっていました。中でも、第91条第2項による「映画に収録された実演をさらに録音、録画することについては、レコードなどの録音物に録音する場合を除いて、実演家の権利が働かない」規定と第92条第2項第2号のロによる「映画の増製プリントあるいは旧作映画から作成されたビデオカセットなどを用いる放送、有線送信についても実演家の権利は働かない」規定が、実演家を泣かせてきた事実は決して忘れることの出来ないものになっています。
このようにして、著作権法が新しくなって30年。
「映画」の定義さえ明確でないまま、「映画の著作物」の権利のあり方を規定している現行著作権法の矛盾を正し、著作権法の中に実演家の権利を正当に盛り込もうという運動は、一時も休むことなく続きます。まさに実演家のここ30年間の歩みは、著作権法の「映画」の矛盾点をいかにして打ち破るかの歩みだったのです。
事業協同組合を目指す
話が少々横道に逸れてしまったようです。大急ぎで元に戻しましょう。
任意団体として発足した放芸協は、そのまま止まることをせず、法人格の取得に動くことになります。
そもそも放芸協は、設立に当たって掲げた「規約」の中で、目的を「この協会は、放送(ラジオおよびテレビジョンをいう)に出演する専門芸能家の提携の場となり、会員相互の親睦と研修によってその技能と品位の向上ならびに福祉の増進をはかり、もってわが国放送文化の発展に寄与することを目的とします」(第4条)と謳いました。そして、目指す事業としては
- 放送出演に関する諸問題について
1.調査研究と意見の発表
2.各放送企業体との協議・調整 - 機関誌の発行および資料の刊行
- 研究会、講演会その他の会合の開催
- 芸能家に対する放送専門教育機関の設置および運営
- 放送芸能家会館の設置および運営
- 関係文化団体との連絡、提携
- 放送芸能家の国際交流
- 放送文化の向上に寄与した団体ならびに個人の顕彰、および研究の奨励
- 会員の親睦、共済、および福祉厚生をはかる諸事業
- その他、前条の目的を達成するために必要な事業(以上、第5条に記載)
を掲げています。しかし、このように立派な事業目標を掲げても、俳優が放送に出演した際の出演条件を改善していくことには直接つながりません。俳優の出演条件を改善し、俳優の持っている本来の権利を確保するにはどうしたらよいのか。それは、放芸協を結成した直後からの最大の問題でした。
そして、この問題の解決のために大きく前進しようとしたのが事業協同組合の結成だったのです。組合の結成総会は、1967(昭和42)年5月27日、東京・平河町の日本都市センター講堂で行われ、同年7月7日には通商産業省(現経済産業省)の認可を得ることが出来ました。
1967(昭和42)年7月10日発行の放芸協機関誌「放送人」第19号には「ユニオンへの最短コース――放芸協協同組合化の道――」と題する記事が掲載されています。
日本を訪れた外国の芸能家は、この国にはいまだに「ユニオン」がなく、勝手気ままに荒稼ぎできる状態に、驚いたり、呆れたり、喜んだりしています。
彼らの国へ日本の芸能家が行ったときには、そんな目茶は許されません。野放しに誰でも勝手に仕事がやれるようでは、その国の「専門芸能家」の生活が脅かされてしまうからです。そこで彼らは、それぞれの職種によってガッチリと自分たちの砦「クラフト ユニオン(職能組合)」を作っています。
例えば、アメリカでは「放送芸能家連合(AFTRA)」「映画俳優組合」「舞台俳優協会」「演芸家組合」「エキストラ組合」「音楽家組合」等々があってこれらに加入していなければ、いかに実力があるスターといえども、仕事ができない仕組みになっています。なぜなら、それらの組合は各放送会社や映画会社との間に「組合員だけを雇い入れ、組合員以外は使わない。もし組合員以外のものを使いたいときには、30日以内に組合加入の手続きをさせなければいけない」といった種類の(ユニオンショップ制)団体協約を結んでいるからです。
(中略)
日本でも、ただ親睦のための任意団体や社団法人の協会ではない、本格的な「芸能家の組合」を待望する声は、すでに久しいものです。しかし、アメリカとはいささか事情を異にする日本の芸能界にあって、最も私たちの実態に即したユニオンを創設するにはどうすればいいか?どういう形態のものなら可能であろうか?
放芸協は、3年7ヶ月の体験の中で、それを考え続けてきました。
(以下略)
その結実が、「事業協同組合」という組織だったのです。この形態の組合は、労働組合ではありません。「中小企業等協同組合法」という法律に裏付けられて組織される、ある事業目的をもった協同組合です。
太平洋戦争の敗戦後、焼土と化した日本の産業復興のためにはアメリカ駐留軍の指導もあっていろいろな政策が施行されました。とくに、大きな資本が形成されていない段階で各種の産業に生産力を付けて行くためには、協同して資金手当、資材購入、原料確保に当たる必要がありました。日本全国に散在する「鉄工組合」「木工組合」「商店街組合」などは、いずれも、小規模、零細の企業が集まって共同購入や共同の融資によって共存共栄を狙っているものです。
俳優にも同じことが言えます。俳優は、かつての五社体制全盛期のように、大きな映画会社と専属契約を結んで事実上の社員扱いになっている人ならば別ですが、本来は一人一人が独立した事業主になっています。しかし、事業者として規模がこれ以上に小さくなるものはあり得ず、まさに零細を絵に描いたようなものと言えるでしょう。そこで、零細事業主が集まって相互扶助の精神に貫かれた共同体を形成するとしたら、それは事業協同組合、というわけでこの道を選んだのでした。
俳優が事業協同組合を形成した場合の最大のメリットは製作会社との団体協約が締結できるという点でした。中小企業等協同組合法では、組合側が事業者側に団体交渉を申し込んだら、正当な理由がないかぎり、これを拒否することはできないと定めています。もちろん、団体交渉ができたからと言って、すぐに組合側に有利な団体協約が締結できるとは限りません。また、当然のことながらストライキ権もありません。でも、事業者の集まりとして制作者側にはそれなりの都合を主張する権利があります。でも、一人一人の俳優、一社ごとの零細企業では話し合いの機会が持てないのに組合としてまとまれば交渉の機会が得られるのですから、こんな好都合なことはありません。放芸協はこうして職業芸能人の組合として1967(昭和42)年7月7日、通商産業省(現在の経済産業省)から、正式の認可を受けたのでした。
事業協同組合なる法人格を取得するとなれば、その存在価値を文書で記した「定款」が必要になります。放芸協は、1967(昭和42)年4月1日発効の定款として、次のような内容を掲げました。
「本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動および文化活動を促進し、かつ、その経済的社会的地位の向上を図ることを目的とする」
第7条(事業)
「本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う
- 組合員の事業に必要な視聴覚用器材および消耗品の共同購買
組合員の就業条件に関する協定 - 組合員の事業に必要な視聴覚用器材および消耗品の共同購買
組合員の就業条件に関する協定 - 組合員に対する事業資金の貸し付け(手形の割引を含む)および組合員のためにするその借り入れ
- 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
- 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上または組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
- 組合員の福利厚生に関する事業
- 前各号の事業に付帯する事業
第8条(組合員の資格)
「本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
- 放送に関する作品に出演することを主たる事業とし、かつ、30分番組13本相当以上の実績を有する者であること
- 組合の地区内に事業場を有すること
定款の条文は全部で66ヵ条にもなるものですから、まだまだ沢山あります。しかし、大切なことは「放送用ドラマに出演して、それなりの実績を持っている俳優なら誰でも組合員になれる」「組合員になれば、事業資金の貸し付けを受けたり、製作会社と組合との間で締結された団体協約の恩恵を受けたりできる」「組合が実施する福利厚生関係の事業の恩恵が受けられる」ということだったのです。
最初の事業はNHKとの団体協約
事業協同組合となって放芸協が最初に手掛けた事業はNHKとの出演条件に関わる「団体協約」の締結でした。認可が下りた7月7日から4ヶ月強経った1967(昭和42)年11月17日には早くも予備折衝入り、翌1968(昭和43)年4月4日には、正式の交渉を開始するという順調な段取りを踏んでいます。
ただ、この交渉が始まるまでには、放送界をめぐる大きなトラブルが起きていました。創業以来、経営不振が続いている民間放送の東京12チャンネルが、1967(昭和42)年4月以来、TBS(東京放送)やNET(現テレビ朝日)から放送済みのソフトを譲り受け、それを再放送の形で放送してしまうという、現在では考えられないようなことが行われていたのです。経営不振であればこそ、コストを最小限に絞り込んだ営業が行われていたわけです。この再放送に当たって、番組提供側の民間放送局から出演者に支払われる再使用出演料は、本来の出演料の5%~10%。しかも「支払うから受け取りに来い」という態度だったと言われています。
この問題については、芸団協が問題を重視し、東京12チャンネルには再三にわたって
「きちんと実演家の許諾を得るように」と、また番組を提供している放送局へは「問題が解決するまでは番組提供を留保するように」と申し入れていました。しかし、日本テレビなどは、これに対して、「弊社の放出番組はテレビ映画で、いずれも弊社が製作者より放送権を買い取ったものである」と回答し、TBS、NET、フジテレビからは「貴協議会(芸団協のこと)は出演者に対し、如何なる立場にあるのか判明せず」といった回答が寄せられたのでした。放送番組用に作ったドラマでも「テレビ映画」と称して、劇場映画と同じ扱いにしようという放送局の姿勢は、現行の著作権法制定のための議論が進められていたこの頃から、既に貫かれていたのです。NHKも東京12チャンネルへの番組提供を実施しましたが、NHKが出演者に支払った1回分の金額は約600万円だったと記録されています。
そして、やっと問題が解決したのは1968(昭和43)年6月のことでした。そもそも他局に使用済みのソフトを提供するという理不尽な再放送であるうえに、出演者への支払額も極端に少ないとあって、出演者の中には抗議の意味を込めて再放送使用料の受け取りを拒否する人が続出するという事態さえ生じていました。さすがに良心の咎めを感じたのでしょう。東京12チャンネルは「1968(昭和43)年5月をもって協力番組の提供は終了となりました」と芸団協に伝え、「今後6月以降、同様の番組提供を受ける場合は貴協議会(芸団協)と条件を協議したうえで行う」との覚書を交わしました。
一方、そんな折り、NHKでは自社製作した番組の録音、録画物を積極的に海外、国内各地に頒布したり、貸し出したりという営業活動を始めました。NHKサービスセンターという関連企業との連携による営業でした。ただ、東京12チャンネル問題での苦い経験がありましたから、営業開始に当たっては芸団協との間で慎重な「覚書」の取り交わしを行いました。とくに、出演者に対する報酬については、教養・教育番組に関して国内の学校、教育委員会への頒布の場合、他の国内頒布の場合と分けて支払いの率を決めたり、芸能番組に関しては貸し出しだけに止めるなどの細かい規定を設けました。
こうした背景がありましたから、事業協同組合として発足したばかりの放芸協はNHKとの交渉に当たっては、当然慎重に、とは言いつつも決して簡単には後に引かない強い態度で臨みました。交渉に当たったのは放芸協側からは常務理事の佐々木孝丸氏、久松保夫氏、大平透氏、江見俊太郎氏、それに事務局長の村瀬正彦氏らでした。途中、村瀬氏が病に倒れ、常務理事の浮田左武郎氏がピンチヒッター役を受け持ったりもしました。
そして、団体協約が締結となったのは1969(昭和44)年3月6日のことです。
今般、本組合は、日本放送協会との間に、中小企業等協同組合法第9条の2第1項第5号に基づく、団体協約を締結致しましたので、ここにお知らせします。
昭和44年3月6日
協同組合 日本放送芸能家協会
理事長 福 原 駿 雄
(徳 川 夢 声)
法人格を取得した俳優独自の組織として、記念すべき成果の最初の礎石でした。
全部で29条の条文からなるこの団体協約の第2条には「乙(NHK)が甲(放芸協)の組合員に放送番組への出演を依頼する場合は、組合員または組合員の指定する代理人に対し当該番組の放送期日、放送形式、放送地域およびリハーサル・ロケーション・録音・録画の日時、場所など出演スケジュールを提示する。・舞台中継放送の出演の場合には、乙はあらかじめ放送期日、放送地域、収録スケジュールを甲に通知する」の定めがあります。また、最も大切なギャラに関しては、第6条で「出演料の基準料金はテレビジョン放送または音声のみの放送(ラジオ放送のほか、FM放送、国際放送を含む)の別により定め、原則として30分以内の番組への出演に対する料金とする」とし、出演のケースによって細かく計算方法を定めました。
調印を終えた徳川理事長は、その感想を1969(昭和44)年4月1日付けの機関誌「放芸」紙上で、次のように述べておられます。
「一昨年来、もみにもんだ結果、やっとのことで生まれた協約書である。私は目を通している間に、これは大変だったろうと、心から双方の当事者に頭の下がる思いだった。
日本で最初にタレントと放送局のとの間に生まれた書類である。必ずしも利害の一致しない双方の立場である。ここまでもってくるのが、まったく容易なことではない。
勿論、条文の中には、いささか不満の点もないではない。しかし、これはいかなるこの種の協約書においても、どちら側かに言い分はあるのが普通の現象だ。それらは互いに善意をもった話し合いで、機会あるごとに改めていけばよろしい。
私は、二通出来た立派な協約書に、放芸協代表として印を押した」と。
また、団体協約の締結を祝って、当時の文化庁次長、安達健二氏、NHK放送業務部長の川嶋浩氏からも祝辞が寄せられました。
資金集めはクイズ番組で
以前、1965(昭和40)年当時に、フジテレビの「地上最大のクイズ」に俳優が大挙出演して、放芸協の財政の一助になったエピソードを紹介しましたが、こうした動きはそれから3年を過ぎた時点でも続いていました。というよりも、むしろ、テレビ番組への出演による出演料獲得で財政を維持することが常態となった、と言ってもいいのかも知れません。
放芸協は1967(昭和42)年5月に事業協同組合になって以来、内部の組織固めを模索してきましたが、1968(昭和43)年9月には福利厚生委員会(委員長・多々良純氏)、財務委員会(同・池部良氏)、事業委員会(同・淡島千景氏)、紛争処理委員会(同・小泉博氏)、広報委員会(同・浅野進治郎氏)、組織委員会(同・浮田左武郎氏)、資格審査委員会(同・河津清三郎氏)、融資委員会(同・細川俊夫氏)、調査委員会、法規委員会(この2委員会は委員長を置かず)の各委員会を一斉にスタートさせました。その中で、最も活発に動き出したのが事業委員会でした。
事業委員会の役割は「営利を目的とする事業の企画及び折衝連絡ならびに管理に関する事業」となっています。さて、そこで具体的に何を手掛けるかということになったわけですが……、
この頃、大阪に本拠を置くテレビキー局の毎日放送が人気番組「アップダウン・クイズ」を制作、放送(東京ではテレビ朝日の前身であるNETがネット)していました。スタジオ内に作られたエレベーターのような椅子に回答者が座り、正解を出すごとに椅子は上へと上がっていきます。無事に一番高いところまで上がれれば、高額の賞金が獲得できるのですが、途中で間違ってしまうとストンと下まで落っこちて、それまでに稼いだ賞金もパーという具合でした。
毎日放送では、この番組で毎月1回、ゲスト大会を企画し、当代人気の芸能タレントを招待していました。そして、放芸協事業委員会に協力要請が来たのです。張り切ったのは委員長の淡島千景氏でした。自らも出演しましたが、他の組合員にも積極参加を呼び掛け、1968(昭和43)年12月21日の第1回録画を皮切りに、ゲストを送り込んだのでした。クイズで当てた賞金は個人で持ち帰ってもいいことにしましたが、出演料は放芸協の財政に投入ということにし、資金獲得の一助にしたのでした。