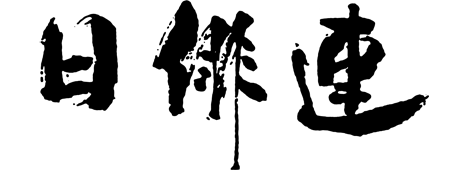-1996年- インターネットに取り組む
「インターネット」――この聞き慣れない言葉を日俳連にもたらしたのは、声優の羽佐間道夫氏でした。放芸協時代からの活動家で、日俳連の理事、常務理事をも再三にわたって経験されている羽佐間氏は、組織体を動かすに当たってデジタル時代の情報発信には積極的に取り組まなければならないことをよく知っていました。ただ、今でこそ小学生でも使いこなせるインターネットも、この当時はまだ、どうすれば開設出来るものか、知る人は稀でした。日俳連事務局にもパソコンは二台配備され、組合員の管理、賦課金の計算、諸文書の作成等にフル稼働していましたが、通信用機器として活用できる状態にはなっていませんでした。
というわけで、「インターネットとは何か」を見学するツァーが企画されました。ツァーとは言っても、バスを連ねて遠路はるばる出掛けるというわけではありません。東京・芝大門の日俳連事務局から歩いて15分程度の新橋にある太陽企画という会社のオフィスにお邪魔したのでした。太陽企画は大手広告代理店、電通の系列会社でインターネット網を利用してのTVコマーシャルなどを製作しています。
1996(平成8)年2月7日、太陽企画を訪れたのは羽佐間氏をはじめ、大林丈史常務理事、粟津號氏、白石奈緒美氏、坂俊一氏、福山象三氏の4理事でした。実際に、アクセスしてもらい同業のエージェンシーが呼び出された時は思わず感嘆の声があがるといった具合で、「では、アメリカのホワイトハウスにアクセス」といわれたときには、クリントン大統領が画面に出てくるのかと期待で胸を膨らませるような状態でした。実際には、回線の混雑でアメリカへは通じず、事なきを得ましたが、一同は時代の変化をつくづく思い知らされるのでした。
俳優にも「労災」適用の道が…
この年3月25日、労働省の主宰する「労働基準法研究会労働契約等法制部会労働者性検討専門部会」(座長・奥山明良成蹊大教授)という長ったらしい名称の専門部会が、俳優や建設業界の個人業者など、企業との雇用関係を持たない者にも「労働災害補償保険」の適用の道を開く見解を発表しました。これは、俳優にとって、待ちに待った一つの朗報でした。
労働災害補償保険、略して「労災」は文字通り労働者が就労現場で死傷事故に遭遇した場合に、被害の程度に応じて国が補償する保険制度です。ビジネスマンであれば出張中の事故、通勤途上の事故でもケースによって適用が認められてきました。ところが、俳優や映画のカメラマン、その他スタッフなどにはほとんど適用されないままできたのです。理由は、俳優や映画のスタッフには労働基準法第9条に定める企業との雇用契約がないから、でした。「雇用関係が明確で、月決めの給料が支払われていなければ労働者とは言えない」。労働省の地域出先機関である労働基準監督署は、この決まりを頑なに守り、誰が見ても労働災害と思われる事故でも、雇用関係の有無を盾に申請を排除し続けたのです。
この矛盾点を取り除いて貰うために、日俳連は長年、労災連(芸能関連労災問題連絡会)と協力関係を保ちつつ、労働省に働きかけを強化してきたのでした。
上記の長ったらしい名称の専門部会が新たに出した見解は、一言でいうなら、「俳優の場合、演技、作業の指揮、監督や演技する場所、時間に関する拘束が明らかならば、労働者性があり、労災の対象になり得る」というものでした。認定に不備な点もありますが、これは明らかに、従来の労働省の見解から前進しており、日俳連の中にも「これで労災適用の道は開けた」との雰囲気が伝わったものでした。しかし、それからというもの、この見解に沿って芸能界で働く者に労災が適用された例は一つもありません。学者の方々が集まって一定の見解を出しても、役所は簡単には動かない。やはり、適用までには、ねばり強い運動が必要なことを思い知らされる出来事だったのでした。
改めて「契約」を考える
「契約」の問題は、俳優にとっての長いテーマであり、繰り返される課題です。何度繰り返しても定着しない書面契約の励行。書面契約を要求する俳優側の立場の弱さ。そして「書面」の持つ重みに対する認識の不足…。これらを解消するにはどうしたらいいのか。俳優の権利に向けて世界は、いま、どう動いているのか。日俳連は、1996(平成8)年4月23日、マネ協、劇団協、芸俳連(芸団協・俳優関連団体連絡会議)の協賛を得て、東京渋谷区恵比寿のテアトルエコーで「新時代の契約を考える」シンポジウムを開催しました。このシンポのきっかけは、組合員である女優さんのところにテレビドラマの製作会社から「出演するに当たり、出演後の権利はすべて製作会社に帰属する」旨の契約書が送りつけられ、署名、捺印を求められたことでした。
折しもこの年、WIPO(世界知的所有権機関)は年末までに外交会議を開催し、新たに俳優に「人格権」を与えたり、経済的権利を拡大することが出来る新条約を採択しようと検討を進めていました。ドラマの製作会社は、こうした世界的な動向に危機感を抱いたのでしょう。「権利は製作側にある」との実績を書面契約の形で実績として残そうとの思惑も働いたと思われます。
日俳連では、この女優さんに対しては、決して提示された契約書に署名、捺印をしないよう指導・要請するとともに、このような製作会社に反省を促す意味も込めてシンポの開催に踏み切ったのでした。
このシンポにパネリストとして参加した芸団協事務局長の棚野正士氏(現専務理事)は、「実演家の権利に関わる国内的、国際的検討の場の概要について」として、概略次のような報告をしました。
さらに、著作権審議会マルチメディア小委員会のワーキンググループでも別の検討が進められ、実演家の人格権をどう位置づけるかが議論されており、92年5月に設立された「映画の二次利用に関する調査研究協議会」では映画監督、スタッフ、実演家、製作者の間の契約の適正なあり方が検討されています。
他方、海外ではWIPOでの検討が進んでおり、96年12月には、スイスのジュネーブで外交会議の開催が行われることになっています。日本の実演家としては、この外交会議で採択されるであろう新条約が実演家にとって実行力のあるものになるよう運動を展開しなければなりません。運動が実効あるものになるためには、行政府、学会、マスコミ、一般社会に向けて問題を提起、発信する必要があります。そして、発信した問題提起が実を結ぶための社会との、また国際的な連帯が必要にもなるのです。連帯がものを言い、効果を上げてゆく一つの方法として団体協約の締結があるでしょう。このような運動論の確立こそが、俳優の権利拡大の原点です。
これに対して、実態論から契約の重要性を解説したのは顧問弁護士の橋元四郎平氏でした。その内容要旨を再録しますと
すなわち、実演家から放送の許諾しか受けていない場合、テレビ局は放送目的だけに実演を収録できるのであって、それ以外の目的に収録した番組を利用することは出来ません(著作権法第93条)。ですから、ビデオ化して販売するときは実演家から改めて録音録画の許諾を得なければならないのです。ところが、番組への出演が録音録画の許諾として行われたものだと、放送以外の目的に利用されても実演家の権利は及ばないことになってしまいます。
この辺は、製作者側は一生懸命勉強していますから、将来実演家からの文句を出させない手段の一環として、理不尽な契約書への署名や捺印を求めてくるのです。こうなる原因が現行著作権法の規定の仕方にあることは否定できないでしょう。しかし、もう一つよく考えておかねばならないのは、実演家側に権利意識が低く、製作者側の手玉に乗せられてきたという側面も否定できないでしょう。いまこそ、実演家が「自分の権利を守る」「自分の問題として真剣に取り組む」との姿勢を示さなければならないのです。
このシンポジウムでは、最後に参加団体全員の名において「宣言」を発しました。その内容を次に掲げておきましょう。
契約は、私たち芸能実演に携わる者が自らの権利を確保するための基本です。実演家と製作者が対等な立場で契約を結ぶことこそトラブル解消の第一歩なのです。
いま国際的な情報ネットワーク時代に即応しWIPO(世界知的所有権機関)では著作権に関する条約再検討が急ピッチで進められ、とくにデジタル技術の進歩に伴う実演家の権利の見直しや人格権の付与を中心に新しい条約が生まれようとしています。
わが国でも一昨年来マルチメディア時代における著作権問題を協議するため、権利者、利用者双方の協議会が生まれ、精力的に研究が進められています。
一方、文化庁が設けた「映画の二次利用に関する調査研究協議会」も、適正な契約による二次利用のルール作りを目指して、3年半に及ぶ検討を重ね、いまそのまとめが作られようとしているところです。
このような実演家にとって何十年に一度の条約や制度上の重要な見直しが進められ、実態的にも将来を見据えた合理的な契約慣行の樹立が望まれているときに、最近一部の映画製作者や放送事業者の間に、出演時の1回の報酬で、出演目的以外の全ての利用における実演家の権利を放棄させるような契約を要求する動きが強まっています。このような動きは私たち出演者の権利を守ろうとする者にとってゆるがせに出来ない、極めて憂慮すべき事態であります。
私たちは、新しい時代に向けて内外に重要な動きのあるこの大事なときに当たり、一方的に製作者の利益を押しつけるような旧態依然たる契約を拒否し、21世紀に即した適正公平な契約の実現を目指して努力することを「新時代の契約を考えるシンポジウム」の決意としてここに宣言します。
1996年4月23日
協同組合日本俳優連合、日本芸能マネージメント事業者協会、社団法人日本劇団協議会、芸団協・俳優関連団体連絡会議(関西俳優協議会、名古屋放送芸能家協議会、社団法人日本映画俳優協会、社団法人日本喜劇人協会、日本新劇俳優協会、日本児童青少年演劇劇団協議会、日本人形劇人協会、社団法人日本俳優協会、人形浄瑠璃文楽座、社団法人能楽協会、日本演出者協会、日本舞台監督協議会)
オーディション料はどうなった?
テレビのコマーシャルや販売促進、教育用ビデオなどの製作に当たって、出演者を決めるオーディションがよく行われます。ところが、かつてはオーディションのために集められた俳優やモデルには支払われていた「オーディション料」が、最近は、ほとんど支払われなくなってしまいました。
時間を拘束されて、交通費も自己負担して出掛けてゆくのに終わってしまえば知らん顔、採用しなくてもそのまんま、というのではいかにも不合理ではないでしょうか。日俳連の組合員からも強い不満が続出していましたが、日俳連に限らずモデルを専門とする人からも出されるようになってきました。
そこで、日俳連、マネ協、劇団協、日本モデルエージェンシー協会の4者は連名で各広告代理店、キャスティング会社、コマーシャル製作会社300数十社、その他団体数カ所に申入書を送付しました。
その要旨は、概ね次のようなものです。
- オーディション会場には一つの役に数十人という出演候補者が集められる場合があり、出演の機会を得る確立は非常に低い。しかも、昨今は交通費等費用の負担をして集まる俳優、モデルにオーディション料を支払わないのが慣習のようになってしまいました。
- オーディションの役柄に合ったキャラクターを集めるための事前の絞り込みを十分に行っていないのではないかと思われるふしがある。
- 多人数を集めることが、キャスティング事務所の実力を広告代理店にPRする手段として使われているきらいがある。
- 多くの演技者に演技をさせ、そのアイディアを利用して製作プランを固めるのに役立てているケースがあるように見受けられる。
- 会場に演出者が立ち会わず、流れ作業でビデオカメラに向かって演技をさせられる。
- 担当者の俳優に対する応対が無礼でぞんざいなことが多い。
このような好ましくない実態を解消するために、1996年9月1日以降行われるオーディションに関しては1人1件につき、最低5000円の「オーディション料」を申し受けます。
しかし、この申し入れ書の効果はあまり高くありませんでした。「第1次のオーディションは我慢していただき、第2次の際には払うから…」、などと申し入れ後に何らかの誠意を見せるところもありましたが、徐々に減り、不況の深刻化とも相俟って、結局「オーディション料問題」は徐々に沙汰消えとなってしまいます。
姿が見えると権利が消える
この奇妙きてれつな見出しは、1996(平成8年)12月20日にスイス・ジュネーブの外交会議で採択され、2002(平成14)年1月1日に発効した「WIPO実演・レコード条約」(略称WPPT=WIPO Performers and Phonogram Treaty)の中身を端的に言い表したものです。実演家が映画の撮影時に主題歌やバックミュージックを演奏し、その音楽がサウンドトラックとしてレコードやCD、カセットテープで売り出されると実演家には二次利用料が支払われます。しかし、その同じ映画をLD(レーザー・ディスク)やビデオテープで売り出したら、同じ出演者でありながら、また全く同じ実演活動をしたのに、二次利用料は一銭も受け取ることが出来ないのです。
この奇妙な権利の変質、すなわち「姿が見えると、同じ実演家の権利が消えてしまう」ことを正当化したのがWPPTだったのです。なぜ、こんな奇妙なことが平然とまかり通ったのでしょうか。それは、一言で言うならアメリカの“ハリウッド資本”、すなわち巨大映画会社の力がアメリカ政府を動かし、果ては130カ国以上もの国が参加しているWIPOのおおかたの意向をも無視し、押し切る形で自らの利益を守ろうとしたからです。
“ハリウッド資本”によるアメリカ映画産業は、世界中の映画市場を席巻してしまったと言っても決して過言ではありません。そしてその圧倒的な力を背景に、徹底的に利益を追求するというどん欲な姿勢を貫いているのです。アメリカという国は、さまざまな点で世界をリードする先進国であるにもかかわらず、こと著作権に関してはものの考え方が極端に遅れています。「著作隣接権」に関しては法規定はおろか概念すらなく、法整備によって実演家を保護しようなどとの考え方は存在しません。
では、俳優や音楽家などが映画に出演した際に二次使用料を払って欲しいと考えた場合にはどうするのでしょうか。
実演家は労働組合に結集してストライキ権を背景に要求を勝ち取るという形態をとっているのです。組合員約7万人を擁するSAG(スクリーン・アクターズ・ギルド)という労組は、「マフィアか?」とからかわれるほどの組織力にものを言わせ、組合員の利益のために製作者と交渉して団体協約を、そして、さらに個人々々書面契約を勝ち取ります。それはあくまでも「契約」によって勝ち取ったものであり、法律の裏付けに基づいた「権利の成果」ではないのです。ですから、実演家は労働組合の力によって出演後にも一定の報酬を保証されますが、逆に、労働組合に加入しなければ出演さえできないという制約も受けているのです。従って、ハリウッド資本の製作者たちは「実演家が二次的な報酬が欲しければ、契約を結んで勝ち取ればいいのだ。なにも国際条約や国内の法律を作ってまで保護してやる必要はない」と考え、自国の政府に対しても「国際会議の席で主張するように」と、ごり押しをするのです。
96年12月の外交会議では、まさに、このアメリカの論理が押し通され、会議は混乱状態に陥りました。多数決で結論を出そうと思えば、圧倒的多数でアメリカのごり押しは否決されたでしょう。だが、WIPOの外交会議はあくまでも全会一致を旨とし、それが出来ないときには政治的な決着に委ねることにしています。というわけで、最後にはクリントン米大統領とサンテールEC委員長が電話で話し合い、「映像の権利は見送り」との結論を全世界に押しつけてしまったのです。理不尽な結論に怒ったアフリカの国々からは、採択されたWPPTに付帯決議を付けることが提案され、「視聴覚実演に関わる実演家の権利を1997年を超えない移転で確立させる」との決議文が、アメリカをも含めた、全会一致で採択されました。
しかし…。
この付帯決議は採択されたものの、視聴覚実演を巡る検討はその後4年にわたる討議にもかかわらず、結論をみることが出来なくなってしまったのです。再び生じるハリウッド資本の抵抗。その詳細は2000(平成12)年のところで詳述することにします。
総理大臣に直訴
二十一世紀を目前にしたいま、世界に冠たる「文化立国」に向けての努力は、日本がなすべき重点目標の大きな柱と言っても過言ではないでしょう。映像に、舞台に、音声製作に、より高度で芸術的な作品づくりを求めて俳優が活動範囲の拡大を要求するのもこの大きな目標を達成しようという意気込みの表れに他なりません。研修と研鑽、さらには社会貢献もまた新たな「文化立国」の中で俳優に課せられる大切な務めです。
しかし、翻って、現在俳優に与えられている環境はあまりにも劣悪と言わざるを得ないでしょう。形の上では自由を標榜し、「対等」を旨としながら、契約や出演条件の上ではごく一部の例外をのぞいてほとんどの俳優が製作会社や放送局に主導権を握られ、主体性を発揮できないでいるのが実情です。その原因は現行著作権法上で俳優を「著作隣接権者」と位置づけながら、事実上の骨抜き条項ともいえる例外規定が設けられていることに由来します。そして近年、デジタル技術の発展に伴い映像や音声の合成、改変が可能になって、俳優の名誉、声望が多大に侵害される可能性が出てきました。これはひとえに、俳優に著作権法上の「人格権」が与えられていないことが原因だと考えられます。こうした問題点は、大なり小なり世界各国の俳優と共通するもので、国際俳優連盟(FIA)も強く主張しているところです。
そこで、私たち日本の俳優は、著作権法上での人格権及び経済的権利が全て認められることを、そして、本年十二月から世界知的所有権期間(WIPO)の場で検討されようとしている「実演家及びレコード製作者の権利を保護する条約」でわが国の著作権法で欠落している視聴覚著作物における実演家の権利が明確に位置づけられることを、強く希望します。俳優として働く人間として当然の権利が保障され、安心して活動できる環境が整備されてこそ、二十一世紀の文化創造に向けての一翼が担えると考えるからです。
政府機関で働く皆さま、国政に携わる国会議員の皆さまに私たち俳優の、この切なる願いがお分かりいただけることを願って止みません。
平成8年11月11日
協同組合 日本俳優連合
これは、1996(平成8)年11月11日、衆議院第一議員会館で開催した日俳連主催の集会での宣言です。
WIPOの外交会議で「実演家の人格権」などの確立を期待した日俳連では、この日の集会後、森繁理事長、二谷専務理事、三崎千恵子氏が橋本龍太郎首相を訪問し、直々に「日本政府が実演家の立場に立って外交会議に臨むよう指示していただきたい」と訴えました。古川事務局長が、以前からの知己であった内閣官房副長官で参議院議員の藁科満治氏を通して首相官邸に連絡したところ、面会に応じていただけたのでした。
前にも記してきたように、日本の著作権法はローマ条約を下敷きに条文が作られており、実演家に関しては「著作隣接権」を認めてはいながら、著作者に認められた「人格権」すなわち「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」を認めてこなかったのです。著作者である作家や作曲家と実演家とは、普段の創作活動は、質的に違ってはいます。しかし、小説が映画化されるときには俳優の演技によってその小説の良さが引き立てられるのであり、作曲者の書いた名曲も演奏者が奏でてこそはじめて音楽として生きてくるのです。だから、本来、著作者に与えられる「人格権」は実演家にも認められるべきなのに、どうして差別が生じるのか。国際条約(ローマ条約)が認めていないから国内法で規定できないと言うのなら、その国際条約を修正するのに政府として努力していただきたい。
この理屈を橋本首相はよく分かってくれました。「創作活動に従事する者が当然与えられるべき権利を持つのは自然の摂理だ」と首相は語り、外交会議に出席する文化庁など日本政府の代表には伝えておく、と約束してくれました。
ただ、橋本首相はこう語った後で次のように付け加えることを忘れませんでした。
「権利を主張するのはいい。俳優さんの主張は正しいと考えています。しかし、権利を認められるかどうか、また、認められた権利をどう活用するかは俳優さん自身の大きな課題です。権利を勝ち取ろうとするなら自ら努力することが大切だし、勝ち取った権利は自ら守らなくちゃだめですよ。とかく、俳優さんは権利がない、恵まれないと不満を述べるけれど、その不満の解消のために自分から積極的に身体を動かすことが少ないのではないですか」
いささか、耳の痛い話でした。
文化庁長官にも
「実演家の人格権」「映像作品出演に関わる経済的権利」の確立を目指す日俳連は、政府に向けて約1万4000人の署名を集めていました。これを文化庁に届けることにし、この年11月26日には、日俳連から江見俊太郎副理事長、高城淳一、大林丈史両常務理事、古川和事務局長、それに日本音楽家ユニオンの松本伸二事務局長が吉田茂文化庁長官を訪問。署名簿を提出しました。
「社会参加の会」が発足
実演家の権利拡大を施行する一方で「ただ求めるだけでなく、自らの活動を社会に有効に還元するため何かすることはないか」という課題に取り組むことが検討されてきました。とくに、迫り来る高齢化社会への対処は、実演家にとっても他人事ではなく、社会全般の動向に伴って積極化せねばならない必然的なテーマになってきました。
この課題に正面から取り組もうとして動き出したのが「社会参加の会」です。言ってみれば、「俳優の未来を考える会」の討議の中から派生してきた新しい活動でもあったのです。この会は、この年から常務理事に就任した内田勝正氏を中心に組織の結成と具体的な活動テーマが検討されました。世話人として集まったのは同じく新たに常務理事となった浜田晃氏と理事の粟津號氏と中村孝雄氏、それに市川治氏、福永典明氏、本阿弥周子氏でした。
検討の結果、取り組む事業の柱は「組合員同士の相互扶助」と「俳優の特性を活かした社会貢献」の二つです。そして、より具体的な目標として
組合員同士の相互扶助では
- 高齢組合員及び病気療養中の組合員に対するケア
- 俳優の職業病に関する情報交換
を中心に
俳優の特性を活かした社会貢献では
- 視聴覚障害者向けの朗読テープ作り
- )海外の難民のための資金援助
- 地域ボランティアを組み込んだ演劇活動
- 地域自治体の社会教育への協力
- 日本赤十字社の献血キャンペーンへの協力
- )俳優と一般の人々とのふれあう場の設定
を進めることにしました。