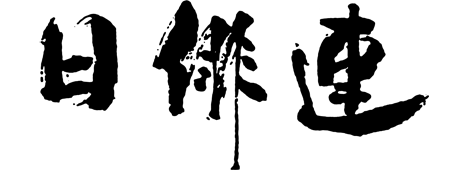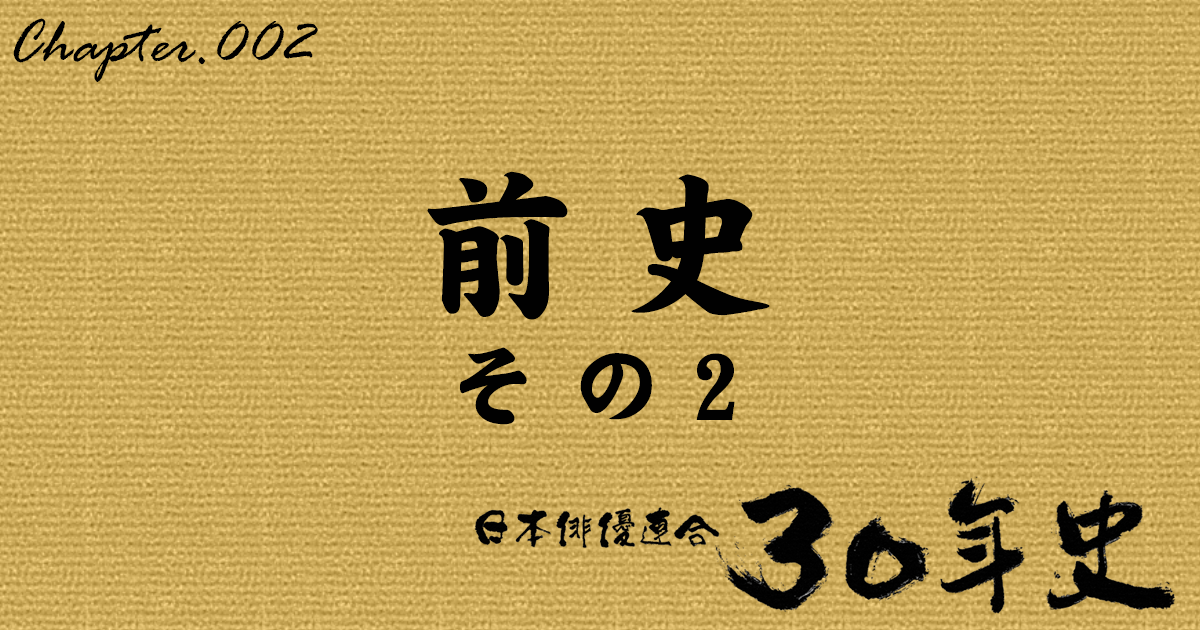-1978年- ヨーロッパ放送業界研修ツアー
俳優としての生活条件悪化が深刻化する中、ヨーロッパでの放送番組製作の実情はどうなっているのか? それを現地でつぶさに調査しようというツアーが芸団協の助成を受けて実施されました。主催は放芸協をはじめ、日本放送作家協会、放送批評懇談会、日本婦人放送者懇談会、日本映画・テレビ制作者協会の5団体。参加者は各団体から22人に及ぶ大デレゲーション。期間は2月11日~24日の2週間で、放芸協からは江見俊太郎常務理事と鈴木瑞穂氏、松風はる美氏の3人が参加しました。訪問先はバイエルン放送局(西ドイツ)、国営第2放送局(フランス)、SFP(フランスの番組製作会社)、グラナダテレビ局(イギリス)、BBC放送局(イギリス)、ロンドン・ウィークエンド・テレビ局(イギリス)。そして、その他にモンテカルロ国際テレビスティバル、パリ現代音楽研究センター、ロンドン・オールド・ビック劇場、フランス俳優組合(SFA)、フランス作家ギルド、イギリス俳優エクイティ、FIA(国際俳優連盟)事務局長宅をも訪れて懇談をしました。その時の印象を調査団は次のように報告しています。
ヨーロッパ各国放送局の状況を総括すると
- 製作期間は長く、制作費が多い。
- 公共放送が主流をなしており、受信料収入が主たる財源であるため、(広告収入のために)視聴率競争に血道を上げる日本とは様相が違う。
- ただし、公共放送としての経営状態は苦しいようで、民間商業放送に移行する傾向が見える。
- 下請け制作に関して、放送局が無責任な態度をとるようなことはなく、困ったときは政府の援助がある。
- ドラマの放送本数は日本より遙かに少ない。放送出演だけで生活できる俳優やライターの数は全体の16%くらいで、日本とあまり変わりない。(日本はドラマの制作本数が多いから、出演料や脚本料が低額ということになる)
- 地域別の制作体制を大切にしている。
とのことでした。
外画日本語版のリピート問題決着
1978(昭和53)年6月13日、日俳連の久松保夫副理事長、大平透常務理事、村瀬正彦事務局長は、マネ協の垣内健二理事長、新劇団協議会の鈴木文弥常任理事らとともに、NHK内のテレビ・ラジオ記者会で記者会見を行い、外国映画日本語版のリピート問題が解決に至ったことを報告しました。
日本語版の音声制作に出演しながら、再放送時にリピート料を支払ってもらえない件については、外国映画の放送が始まって以来10数年にわたって、難航してきた問題でした。しかし、1973(昭和48)年7月から8月にかけて、声優による都内のデモ行進、24時間番組出演拒否などの実力行使によって、出演料体系が平均3.14倍の値上げとなり、時間外割り増しも20%から50%に引き上げられることになったのに伴い、リピート両問題も解決に向けての交渉が開かれることになっていました。
1976(昭和51)年4月、放送各社が「時代の趨勢その他によって、何らかの形でリピート料を支払うことはやむを得ないであろうと考えている」と公式見解を出したところから問題解決の道は大きく開かれました。1年余にわたる粘り強い交渉が繰り返されたあげく
- 日本語版テープの利用期間は、最初の放送日から起算して5カ年間とし、この期間中の放送に限り、無制限の使用を認める。
- 前項の期間を経過した後の再使用は、別に定められた使用料を支払う。
の結論に達したのでした。この合意内容は日本音声制作連盟(略称・音声連)に加盟する10社ならびに関連する外国映画配給会社19社と文書によって取り交わされ、以後、定着することになります。
日俳連が法人化に向かう
放芸協とは、まだ、別組織であった日俳連を将来に向けてどう育成していくかは、当時の大きな問題でした。芸団協や日本映画俳優協会、歌舞伎俳優を主体として組織している日本俳優協会がそうであるように、社団法人の形式をとるか、思い切って「労働組合」に再組織するか、自営業者の集まりとしての商業組合を選択すべきか、など議論は幅広く進められていました。1978(昭和53)年10月7日に開催した第5回日俳連全国大会、同年12月15日の第37回常任理事会では、この問題が集中的に討議されましたが、そこで得られた結論は「やはり、事業協同組合で行こう」でした。
「労働組合ならストライキ権があり、強力かも知れないが、芸術家指向の強い俳優の組織にはなじまない」という意見がある一方で
「放送局や製作会社との交渉を行い、協定を締結する権利を確保するには団体交渉権のある組織であればよい」
との意見もあり、議論が何度も繰り返された結果、事業協同組合を選択するとの結論に達したのです。ただ問題は、すでに放芸協が取得している組合の資格をどうするか、でした。日俳連には放芸協の組合員がほぼ全員加わっています。だから、放芸協にしてみれば、既に取得している資格を日俳連に譲り、事業協同組合として移行してしまうのが都合がいい。そこで、放芸協は、1979年5月28日開催の第12回通常総代会に定款改正を議題として掲げ、日俳連の事業協同組合への移行を提案したのでした。
-1979年- 放芸協、日俳連が統合へ
1979(昭和54)年10月15日、放芸協は臨時総代会を開き、定款の変更について承認を求めました。これまで「放送に関する作品に出演することを主たる業とする」小規模事業者の組合であることから脱却し、広く「俳優を業とする者」を主たる構成員とする組合、すなわち日本放送芸能家協会と日本俳優連合を統合し、発展させようとの趣旨に基づく定款の変更でした。
これまで縷々説明してきたように、1963(昭和38)年に設立された放芸協と1971(昭和46)年に創立された日俳連は事務所と事務局長とを同じくしてはいたものの、実際は別組織のままであったのです。ですから、これを統合するにはそれぞれの組織での討議とそれぞれの組織内での合意が必要でした。日俳連1978(昭和53)年12月15日の第37回常任理事会で、一方、放芸協では同じく78年5月の通常総代会で、両組織の統合の方向性を確認していました。こうして提案されたのが新しい定款です。
新しい定款では、第2条「名称」のところで、はっきりと「本組合は、協同組合日本俳優連合と称する」と謳いました。また、第7条「組合の事業」では、放芸協時代の団体協約の締結や福利厚生に関する事業に加えて、「組合員の著作隣接権の行使に係る権利及びその権利を行使した場合の使用料、補償金等の受領に関する事務の代行」という実演家の基本権にかかわる事業を明確に打ち出しました。
また、第8条「組合員の資格」では、「地区内(日本全国)において、演劇、映画及び放送等の作品を製作または制作する事業者(関連事業者を含む)に対し、実演を行いまたは供与することを業とする、次に掲げる小規模事業者とする。
(1)俳優その他の演者であって別表・に掲げる者。
(2)前号の者のマネージメントをする者」
とし、マネージャーをも仲間に入れたのが特徴でした。ここで、少々気になる言葉遣いとして「製作」と「制作」との区別があげられます。製作とは「会社」で行うもの、「制作」とは「個人」で行うものを意味していると規定。また、組合員の中にマネージャーをも加えようとしたのは、俳優とマネージャーが利害を相共にする立場にあるところから、業界の近代化のためには参加を促すことが組合の発展に役立つと考えられたからでした。
いうまでもなく、定款改正提案は満場一致で採択され、1979(昭和54)年11月6日に通商産業大臣への認可申請が出され、翌80(昭和55)年3月17日、認可が下りました。
残された問題
通産省の認可によって「協同組合 日本俳優連合」は誕生しました。しかし、俳優の力による日本で初の、しかも中小企業等協同組合法に裏付けされた唯一の団体交渉権を持った組織が出来たという喜びの一方で、難しい問題が残されたことも見逃すことが出来ません。それは、真にユニオンを目指した全俳優のための組織に発展させるための具体的な方策ならびに任意団体として残された放芸協をどう扱うかの問題でした。
繰り返しになりますが、そもそも「日本俳優連合」は芸能活動を職業とする者が大結束を果たすための「四つの連合構想」に基づいて創立された組織でした。音楽家が結束する「ユニオン日本音楽家連合」、踊りの分野の人々の「ユニオン日本舞踊家連合」、落語、漫才、曲芸などの「ユニオン日本演芸家連合」、そして「ユニオン日本俳優連合」の四つの連合が並列して総連合体である「日本芸能家総連合」、すなわち現在ある公益法人としての芸団協の対局におくべき権利擁護団体として総連合を作るという構想でした。「ユニオン日本俳優連合」の中には放芸協をはじめ日本映画俳優協会、日本喜劇人協会、日本俳優協会(歌舞伎、新派)、能楽協会、文楽座(浄瑠璃)、日本新劇俳優協会、新劇団協議会、関西俳優協議会、名古屋放芸協など傘下の個人全てが参画し、強力な体制が組まれるという構想でした。ですから、この日俳連の初期の会長には日本の輝ける伝統芸能である能楽の部門から初代会長として宝生九郎氏が、第二代会長として喜多実氏が選出され、理事長には新劇(舞台)部門から初代に東野英治郎氏、第2代に永井智雄氏が選出されるといった経緯を辿ってきました。これだけの部門の人々を統合すれば組合員が3000人を超えるユニオンが結成できる見込みでもありました。
ところが、実際には日俳連は協同組合日本放送芸能家協会を引き継ぎ、これに映俳協と新劇俳優協会から何人かの人々が参加する形で決着してしまいました。こうなると、問題は残ります。協同組合としての法人格を日俳連に渡し、任意団体となった放芸協をどうするか、日俳連に結集しきれなかった俳優部門の人々とどう連携してゆくのか、日俳連自体の組織強化、人員増強ををどう進めるのか、この問題はその後延々として残る問題なのでした。
FISTVの執行委への参加
FISTAVとは国際映画放送労働組合連盟の略語です。1974(昭和49)年2月にロンドンで設立されたこの団体は、世界各国のテレビ、ラジオ、映画、現像など放送、映画に関わるスタッフの結集した組織ですが、23カ国、30組合の労働組合で組織され、日本からは映画演劇関連産業労組共闘会議(略称・映演共闘)、民間放送労働組合連合(略称・民放労連)が加入していました。そのFISTAVの執行委員会が1979(昭和54)年6月12~15日、東京・青山の日本青年館で開催されたのでした。
日俳連は、前年(1978年)にFIAに正式加盟した経緯もあり、国際的活動を強化する目的と将来のユニオン化に向けての準備の意味も込めてこの執行委員会に参加、日本の俳優が置かれている現状を二谷英明専務理事が訴えました。また、参加者全員で作り上げた次のような「決議」にも「日本俳優連合」の名を連ねました。
「実演家の権利についてのシンポジウムにおける決議」で重視された部分は、ローマ条約の批准促進と商業用レコードの利用で犯される実演家の権利をどう擁護するかでした。1961(昭和36)年、ローマで採択された「実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約」(略称・「隣接権条約」または「ローマ条約」)は著作物を公衆に伝達する役割を担うものとして俳優、演奏家などの実演家、放送事業者、レコード製作者を著作者と分けて「著作隣接権者」と位置づけました。ところが、実演家は個人(自然人)であるのに対し、放送事業者、レコード製作者は企業(法人)であり、業者によっては大資本に裏打ちされた強力な力を持っています。中でも、レコード製作者が作ったレコードが放送事業者によって使われれば、いとも簡単に、実演家の出演の機会となるべきはずの多量の番組が奪われてしまうという現実があります。それに録音機器に関わる技術の進歩によって私的な複製が容易になり、この面での実演家の権利に対する侵害も深刻になってきていました。「決議」はこの辺を重視し、実演家の権利を護る国際的な協力や、当時まだ22カ国しか批准していなかったローマ条約への各国の批准促進を謳いました。
日本では、その後、1984(昭和59)年の著作権法改正によって、貸しレコードに関する実演家の権利擁護が定められ、1989(平成元)年にはローマ条約への加入が実現することになります。