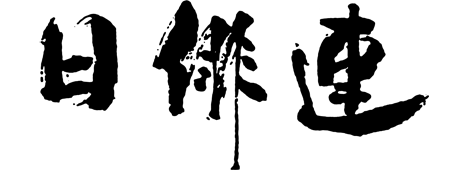目次
-1997年- 日本赤十字社への献血キャンペーン
上記「社会参加の会」が具体的に動き出し、最初に取り組んだのが日本赤十字社の展開している献血運動への協力です。1997(平成9)年2月27日、東京のJR新橋駅前広場に集結した社会参加の会世話人をはじめ有志24人日俳連組合員は、「愛の献血」などと書かれたプラカードを掲げて通りすがりの人々に、献血に協力していただけるよう呼びかけたのでした。最初は、大声を上げる俳優の姿を遠巻きにしていた街行く人々も、そのうちには「あら! 水戸黄門に出ている俳優さんじゃないかしら」「あ、あの人見たことある」とささやき合い、握手を求めに寄ってくる光景も見られるようになりました。その頃には、俳優の社会貢献にニュース性を見出したのか、UHFテレビ局のMXテレビがカメラを担いで取材に来るようになり、インタビューを求められた常務理事もいました。
献血を呼びかけるために用意したティッシュペーパー3000個は1時間でなくなり、あとは日頃鍛えた声での“呼び込み”。お陰で、俳優の呼びかけに応じてくれた人は、後を絶たず、日赤の担当者によると「通常の約2倍の人が応じてくれました。やはり、吸引力は違いますね」との結果が出ました。
社会参加の会、初のイベント参加としては大成功に終わった半日の活動でした。
チャリティ・ウォークの開始
社会参加の会、第2弾の取り組みは「チャリティ・ウォーク」でした。1997年5月10日には、組合員だけでなく、一般の参加希望者にも呼びかけて午前10時に東京・江東区の木場公園に集まっていただき、東雲、有明、青海といった東京湾ベイエリアを歩く企画を立てました。ただ、未経験のイベントでは事故でも発生すると事後処理が難しい問題となります。そこで、この最初の試みは千代田生命保険の外郭団体である財団法人・千代田生命健康開発財団と社団法人・日本歩け歩け協会の主催する事業への相乗りという形をとったのでした。常務理事の内田勝正氏が千代田生命側と細かく打ち合わせを行い、傷害保険の手配など、一般から参加してくださる人たちへの万全の対策を取りました。
イベントの当日、広い木場公園のあちこちに「日本俳優連合」と書かれた幟を立てて、一般参加者を誘導する俳優を見ていたある人が言いました。「今日は、また、何で悪役ばかりが集まっているのだろう」と。もちろん、人相の悪い人ばかりが選ばれて社会参加の会の運営に携わったわけではありません。ただ、時代劇などでは善玉を割り当てられるの主役を張るスター級の人が多いため、「水戸黄門」などで悪徳代官役を受け持つ俳優はみな「悪役」扱いされてしまうのでしょう。「でも、知られている俳優が集まったことで、新しい事業が成功するなら、十分満足すべきだ」。日俳連から参加した世話人たちは、そういって喜んだものでした。
この日参加した日俳連組合員での最高齢者は81歳の現役俳優、岩城力也氏。「もう高齢だからね。歩けやしないよ」と言いながらも10キロコースに参加して、3キロ地点でダウン。「若いときに骨折した足の付け根が痛んでしまって…」と悔やむ一幕もありましたが、積極的なその姿には若い組合員は心から敬服するのでした。
文化立国に向けて何をするか
バブル経済の崩壊以降、経済施策に有効な打つ手が見いだせなくなったためか、真の先進国たるには文化政策の拡大充実が不可欠と考えられるようになったためか、「文化立国に向けて」のキャンペーンが官界、政界でも活発化するようになってきました。その一つが文化庁の「いまこそ文化立国21プラン」であり、二つ目がこれを受けての政界の反応です。
文化庁の「いまこそ文化立国21プラン」は、実は、1996(平成8)年7月に考え方がまとまり、発表されたものでした。その中には3つの理念が示されています。
第一は、物の豊かさから心の豊かさへの脱皮。つまり、輸出拡大を最大の目標とし、市場開拓主導で進められてきた経済施策から脱皮し、伝統文化の見直しや新たなる芸術創造を世界に向けて発進していこうという発想です。
第二は、経済フロンティアの開拓といい、物質的に向上した国民の生活水準を背景として、演劇、音楽、舞踊などの上演ホールの建設や映像ソフトの開発などに新しい産業の目玉を見出していこうという考え方。
そして第三は、国がなすべき援助の方法の模索となります。
こうした理念に基づく具体的施策を列挙してみると、
- 新国立劇場、新構想博物館、ナショナルギャラリーの整備の推進
- 青少年芸術劇場、移動芸術祭、舞台芸術ふれあい教室などによる文化に親しむ機会の充実
- 伝統文化・文化財保存技術の後継者養成支援の推進
- 歴史文化拠点都市総合保全事業
- マルチメディアによる文化財保存活用方策の調査研究
となり、その施策の推進のために、政府は1997(平成9)年度予算案で、文化庁関係費を前年比10.4%増の828億4000万円を要求しました。ところが、このような予算の大幅増加要求を出しても日本の文化関係予算が総予算に占める割合は、0.11%に過ぎず、フランスの0.94%、イギリスの0.33%、ドイツの0.26%に比べると低いことが指摘されています。そこで、事態を改善するためにどう対処したらいいか、で政治の役割が大きくクローズアップされることになります。
1997(平成9)年2月23日、東京・赤坂の全日空ホテルでは、第2回「文化立国・文化省を設立する会」総会が開催され、各政党がそれぞれの文化政策を披露したのでした。その中からいくつかを披露しますと、
自民党の畑恵参議院議員は「全国を10~12のブロックに分け、それぞれに文化の拠点を置く。その拠点には中心となるメセナ(企業から文化活動に必要な拠出金を出して貰う方式)のネットワークを配置する。ネットワークを通じて人材を確保し、イベントなどが企画、実行されるようになる。そのための基本構想はあたらに設立する文化省が立案する」と構想をぶち上げました。
民主党の枝野幸男衆議院議員は「NPO法の成立が必要」と主張を展開しました。その主張の基盤には「文化立国への道程は民間の力で推進すべきで、官主導であるべきではない」の思想が流れています。「NPO法」は、営利を目指さず、演劇、演奏などの事業を行う法人には税制上の優遇措置を与えようという構想です。ところが、過去の行政の歴史を繙きますと優遇措置をする際には必ず監督官庁の許認可がなくてはならず、認可が与えられると、その後数々の規制が加えられるというのが通例になってきました。官庁の顔色を窺い、お叱りを避けるようなことでは文化活動など出来るものではない、と枝野議員は言い、「優遇措置をいただくことを目的に事前のチェックを受けるのではなく、実績を上げた後に優遇措置の申請が出来るシステムに転換すべきだ」と主張しました。
共産党の緒方靖夫参議院議員は「パリの有名なオペラ座では入場料の最高が350フラン(日本円で7000円程度)で、最低は30フラン(600円程度)。また、ルーブル美術館は週に2度、夜10時まで開館している。日本では考えられないサービスシステムだ。また、一般に消費税が高いヨーロッパでも入場料などには税をかけない。なぜなら、それは反文化的だという考え方が定着しているから」といい、大胆な発想の転換が必要なのだと強調しました。
こうした考え方は、やがて、芸団協で検討する「芸術文化基本法制定構想」に、また2001(平成13)年12月に施行される「文化芸術振興基本法」へと集約されていきます。
森繁理事長 朝日新聞に投稿
文化政策の充実に向けての論議が高まる中で、実演家の権利こそ文化充実の大きな要因、と日俳連の森繁理事長が朝日新聞紙上で論陣を張りました。1997(平成9)年4月30日付け「論壇」欄でのことです。「実演家の権利確立に著作権法改正を」と題し、時宜にあったその内容を紹介しておきましょう。
しかし、直接文化活動に携わっている人間の生活実態は、大方の想像とは大きくかけ離れている。「文化」と言ってもその幅は広く、奥も深いのだが、この際、俳優を中心に音楽、演芸など芸能実演を職業にしている者を例にとると、わが国の文化政策の貧困さが浮き彫りになる。政府が文化政策の充実を提唱するなら、まず実演家の「権利」を法的にも確立することこそが大切は要素となると私たちは考える。
長引く超低金利と消費税の増税で生活を圧迫されるのは、芸能実演家とて何ら変わりはない。一般のサラリーマンと違って、失業保険や退職金のない実演家は「きょうは…」「明日は…」と待ちこがれている出演依頼がこなければ、無収入のままで放置される。もちろん、病気やケガなどの被災時に備えた「所得補償保険」に加入する方法はある。また、社団法人・日本芸能実演家団体協議会(略称・芸団協)が実施している「芸能人年金」という制度もある。しかし、これらは加入者1人1人が費用を全額負担しなければならないから、出演の機会すなわち仕事がなくなれば保険料や年金の掛け金さえも払えなくなってしまう。
近年、産業界で昇給や雇用の状況が厳しくなっていることは十分承知しているが、芸能界の場合はそれ以上である。プロデューサーから「予算がなくて」と言われ、出演料を削られるのは日常茶飯事で、華やかなのは極く一部のスターに限られる。いや、スターだって決して恵まれてはいない。
一例として映画のテレビ放映について説明するとお分かりいただけるだろう。劇場映画として公開され、人気を博した作品は、早晩テレビで見ることが出来る。旧作名画ともなれば繰り返し放映され、出演した俳優、演奏家たちは再度その実演を披露することになる。
ところが、実演家や技術スタッフに対してはテレビ放映のような映画の二次利用の報酬は全く支払われない。映画を放送局に売った映画会社と放映した放送局が確実に利潤をあげているにもかかわらずである。この事実は、ビデオの販売、レンタルにおいても同じである。
なぜ、こうなるのだろうか。原因は現行著作権法の不備にある。同法には、第91条第2項および第92条第2項のロに実演家の権利の除外規定があり、映画をテレビ放映したり、ビデオに変換するなど二次利用しても、実演家には報酬を要求する権利などないと定められているからである。従って、映画の利用は放送局のコストダウンには役立つが、映画の放映をドラマの製作に代替させることで、実演家たちがテレビに出演するチャンスは減少してしまう。
問題の解決を目指し、1992年に文化庁の音頭取りで「映画の二次利用に関する調査研究協議会」が設立された。が、3年以上にも及ぶ討議にもかかわらず、実演家側と映画会社ならびに放送局側との主張は終始平行線をたどり、文化庁も未だに結論を出していない。
さらに、国際条約でも実演家の権利はないがしろにされようとしている。昨年(1996年)12月にジュネーブで開催された世界知的所有権機関(WIPO)の外交会議で「実演・レコード条約」が採択されたが、アメリカのごり押しによって「ビデオ、レーザーディスク、DVDのような映像を伴う録音、録画等固定物では実演家の権利は働かない」ことになってしまった。多くの国がこの結果に強く反発し、条約にとらわれず、自国の著作権法改正、整備することにより実演家の権利を確保しようと呼びかけている。
多メディア時代に突入して映像作品は多種多様に変化し、国際的にも多岐にわたる利用が研究されている。文化立国を標榜する日本は21世紀の環境を整備するために、早急に著作権法の改正、整備に取り組む必要がある。
この投稿に対する反響は大きく、国会でも問題が取り上げられました。97年6月6日には衆議院文教委員会で新進党(現在は自由党)の池坊保子議員、民主党の肥田美代子議員、共産党の山原健二郎議員が相次いで質問に立ち、「実演家の人格権」について「音の実演と視聴覚実演とを区別すべきではない」との立場から政府はどう対処するのかと追及、これに対して小杉隆文相、小野元之文化庁次長は「WIPOの場で今後検討される視聴覚実演に関する新条約で対等に扱われるよう努力を続ける」と答弁しました。
「契約労働」の考え方
撮影や舞台への出演中に死傷事故に直面しながら労働災害補償保険(労災)の適用を受けられない問題について、芸能界には、かねてから強い不満が出されていました。そして労災の受けられない原因が「労働者」あるいは「労働者性」の定義に関して政府、学者、芸能界ではそれぞれに意見の食い違いがあり、政府は芸能界で労働基準法第9条に定めた雇用契約を持たずに働く者の「労働者性」を認めないところにあることがはっきりしてきました。
この政府の壁はどうしたら打ち破ることが出来るのか? 関係者が頭を悩ませている最中、ILO(国際労働機関)が新しい概念として「契約労働(Contract Labour)」という考え方を示しました。日本語としてはいささかなじみにくいこの言葉の示す意味は、概ね「雇用契約はなされていないが、働くときは企業の指令に基づいて行動が規制される人々の労働形態」ということになります。ILOのイメージの中には建設現場で働く建築請負業者、森林の伐採に当たる業者、港湾で荷役や船舶の整備に当たる請負業者があったようです。これらの人々は、多くの場合個人の自営業者であり、事業主として扱われますが、働き方の形態からは労働者と同じではないかというわけです。
となると、この考え方は俳優のケースにも十分当てはまります。ILOでは「こういう契約労働に従事する人々に対する労働対価の支払い、安全の保障、事故発生時の補償については一切事業主が責任を負う」として、そのための国際条約を作ろうとの動きもあると伝えられました。まさに、安全問題に全力で対処している日俳連にとっては朗報でした。しかし、……。その後、この契約労働(Contact Labour)という言葉は、世界的な非正規雇用労働者の増加とともに経営者側からの異論を受けて「雇用関係(Employment Relations)」と表現が変わり、ILOでの検討が続けられています。
ユネスコで「実演家の権利」討議
UNESCO(国連教育・科学・文化機関)は、1980(昭和65)年、ベオグラード(当時のユーゴスラビアの首都)で開催した総会で「アーティストの地位に関するユネスコ勧告」を採択し、「アーティストは、本人の希望によって、文化的な労働に積極的に従事するものであると認められる権利を有し、」「労働者の地位に属する全ての法的、社会的及び経済的便益を享受する権利を有する」など、芸能実演家を含む芸術家の権利を大幅に認めるべきとの考え方を全世界に向けて提示しました。この考え方は、提示後、世界各国の芸術家に強く支持されながら、時間の経過とともに放置されることになり、日本国内でも多くの人からは忘れ去られる状態になっていました。
ところが、UNESCOはこの勧告に盛られた精神をもう一度再確認し、実行に移す方策を探る目的で、97年6月16日~20日、パリのユネスコ本部で開催された総会でこれを取り上げました。そこで、日俳連では「この際、WIPO条約を実演家全体の権利拡大に向けて修正するよう世界に向けて訴えるためにも、日本の実演家を代表して参加すべきである」と判断し、小笠原弘常務理事と古川和事務局長が総会に出席しました。
総会では、概略次のように発言しました。
「デジタル技術の急速な発展が実演家の権利を侵害しようとしている例は、日本をはじめアジアの国々でも顕著です。従って、新しい技術の開発から実演家を守る努力は大切です。アナログ、デジタルに拘らず、全ての実演家の人格権が全ての実演に及ぶように早急に権利の確立を実現する条約を求めようではありませんか」
これには、総会に出席していた多くの国から賛同の発言が出されました。
東映動画と日本アニメの問題
テレビ放送用に製作されたアニメ作品をビデオに転用して販売、しかも二次利用料の支払いを拒否し続けてきた東映動画(現・東映ビデオ)の問題が、97年3月、ようやく解決しました。同社の作品製作のキャスティング事務を一手に引き受けていた青二プロダクションが「過去に遡って二次利用料を支払う」ことの応じ、日俳連がこれを了承したからです。
この問題は、日俳連が再三「ビデオ化し、販売したものについては日俳連、マネ協、音声連三者の取り決めによる出演規定に則って二次利用料を支払うべき」と要求したのに対し、東映側「出演料は全て俳優の出演時に支払い済みであり、追加料金の支払いはあり得ない」と主張して平行線をたどっていたものです。97年初頭には「東映がこのような態度をとり続けるのなら、同社の作品には日俳連の組合員は出演を辞退する」などとの強硬意見が出されるほど、日俳連・外画動画部会の中では緊迫した雰囲気が生まれたりもしましたが、青二プロの話し合いへの参加で事態は解決に向かったのでした。交渉に向けて精力的に取り組んだのは、理事の池水通洋氏でした。
解決に当たっての日俳連と青二プロとの合意内容は次のとおりです。
- 二次利用料の支払い対象作品は、1986(昭和61)年以降に製作され、ビデオ転用がなされたもの
- 1991(平成3)年の出演条件改定以前に製作された作品については、出演時ランクの30%を転用料率とする
- 改定以降製作された作品については、同40%を転用料率とする。ただし、ビデオ1巻を多数話で構成するときは時間割引は適用しない
- 日俳連は対象作品リスト、出演者名、支払金額を記した明細リストを受領する
- 今後、引き続き青二プロがキャスティング事務を行う作品については、青二プロが転用料を支払う
ところが、「東映問題が解決したら、それに従う」としていた日本アニメーションが、同社の作品に関する二次利用料支払いの約束を反故にしたことから、また、新たな問題が生じました。日本アニメも二次利用料の支払いを滞らせていたのです。日本アニメの音声製作に当たっている同社の事実上の子会社、音響映像システムによりますと「日本アニメは、アニメーション作品を映画の著作物と主張し、著作権法上、俳優(声優)の著作隣接権は除外されるとの認識から、二次利用料は支払う義務がないとの態度をとっており、音声製作に関する経費を音響映像側に支払ってくれない。音響映像は音声連に加盟しており、日俳連・マネ協・音声連間の出演条件規定に従うならば、二次利用料は支払わねばならないかもしれない。しかし、アニメ製作会社で事実上の親会社から経費の支払いがない以上、ない袖は振れない」とのことでした。
日俳連は、再三にわたって話し合い解決を求めましたが、相手方に誠意は感じられず、97年8月に至って、外画動画部会は、97年9月以降に収録の始まる日本アニメの作品「コジコジ」には、出演を辞退するとの方針を決定しました。
外画・動画再放送使用料の個人配分はじまる
日俳連が1973(昭和48)年7月、初めての街頭デモ行進、出演拒否闘争を実施して以来、度重なる交渉によって1981(昭和56)年、外画動画再放送使用料の徴収が開始されました。そして、外国映画に関しては再放送から5年を経過した後(6年目から)、動画(アニメ)の場合は7年を経過した後(8年目から)放送局によって再放送料が支払われる協定が成立したのでした。協定によって支払われた再放送料は関連団体で一定比率により分配されることになり、音声連25%、マネ協5.25%、劇団協2.25%、日俳連本会計18.75%、クレーム基金3.75%、外画動画部会会計45%と決まっていました。同部会ではこの比率で分配された分を、毎年、部会の活動費に当て、余った場合にはそれを積み立てていました。その結果、約1100万円のお金が積み立てられたのです。そこで、これを部会所属の組合員の在籍年数に応じた一定比率で個人に分配することにしたのです。この個人分配の作業は、この年を最初として以後継続的に続いていきます。
「リフレッシュの会」発足
俳優が自らの意思で、自らの技術を磨き直したり、新しい教養を身につけたり、切磋琢磨する機関を作ろうと、俳優の「リフレッシュの会」が発足しました。1997(平成9)年9月9日に、浜田晃常務理事の呼びかけに奥山真佐子氏、河原崎建三氏らが積極的に協力し、日俳連事務局会議室で促進準備会を開き、早速、具体的な事業の展開を討議した結果、次のようなメニューが決まったのでした。
まず一つ目は、日本語の発声訓練を兼ねた「能」と「狂言」の芸の修得。二つ目は、いわゆる演技の復習で、三つ目は乗馬の訓練、さらに希望者があれば「発声」の基礎訓練も、というわけです。
話は順調に進められ、「能・狂言」については大蔵流の真船道朗氏を先生に選び、翌98年の5月から、毎週木曜日に日俳連の会議室を使って希望者による集団での稽古が、また「演技セミナー」は高城淳一氏を指導者として、毎週金曜日、同じく日俳連会議室で稽古が始まりました。指導を希望する受講者は授業料が格安の1回1000円。不足する費用は日俳連の財政から援助することにしました。
俳優のリトレーニングはヨーロッパでは盛んに行われている事業です。国立劇場や王立劇場を持つ国では、劇場が主宰しての訓練所があったり、イギリスのように俳優の組合であるエクイティーが再教育学校を経営しているケースもあります。日本では、さまざまに構想だけは出されながら、現実化しなかったこの事業を日俳連が自主的に手掛けた意味は極めて大きなものと言えましょう。トレーニングを繰り返すうちに、その成果を世間に問うてみたくなるのは俳優ならでは当然の結果。能・狂言では、2年後に、実演を世間に見せる日がやってくるのです。
日俳連単独主催のウォーキング
前年には、千代田生命健康開発事業団や社団法人・日本歩け歩け協会の主催する事業に相乗りした形でスタートしたチャリティ・ウォーキングが、97年9月28日には、日俳連の主催事業として動き出しました。日本歩け歩け協会のものに比べるとスケールは小さいのですが、それでも皇居一周の約5キロを1時間かけて歩こうというものです。キャッチフレーズは「俳優と歩こう」、そして「恵まれない人へのカンパを」です。
独立主催した第1回では、一般からの参加者250人。日俳連組合員からは最高齢者グループの一人、佐伯秀男氏(85歳)をはじめ30人近くが元気に参加して全員完歩。参加者からいただいた500円の参加費と日俳連からの寄付金を合わせた17万円余が遺児の奨学金を扱う「あしなが育英会」に寄付されました。
新国立劇場オープン
伝統芸能の上演を主目的として1966(昭和41)年11月1日に東京・三宅坂に開場した「国立劇場」対し、オペラ、オペレッタ、バレエ、現代劇などを主体に展開する「新国立劇場」が97年10月10日、東京・初台にオープンしました。
しかし、一般のオペラファンや演劇ファンにとっては待望のオープンとなったこの新国立劇場も、運営面に関しては多くの課題を後回しにしたままとなってしまいました。つまり、上演に当たっての製作資金の手当て、出演者の待遇、安全対策、地方のファンへのサービス、上演演目の二次利用に関する規定などが事前に関係者との間で検討されることもなく、放置されたままのオープンとなってしまったからです。とくに、心配された出演者への待遇、安全対策に関しては労災連(芸能関連労災問題連絡会)、芸俳連(芸団協・俳優関連団体連絡会議)が条件整備について新国立劇場運営財団宛に申し入れをしましたが、誠意ある回答が得られないどころか、事実上無視されるありさまでした。このことは、後年、同劇場でのリハーサル中にスタッフが奈落に転落して死亡するという重大事故を引き起こす結果を招きます。
新国立劇場は、国費を800億円も投じて建設した世界に誇る大劇場です。オペラの上演を中心に据えている大ホールは観客席数1800強。客席ののフロア面積と奥行きまで含めた舞台の面積が同じという立派なものです。オペレッタ、ミュージカル、演劇の上演が主体となる中劇場も客席数は1030余あり、舞台から客席にかけての側壁が可動方式になっているなど、新鋭の劇場として期待されてきました。ところが、機械などの設備には十分な配慮をはらっても、その現場で働く人間には配慮しないという実態が露呈されました。日俳連では、オープン早々に運営財団の理事会に対して「出演に関する団体協約の締結」を、協約案を添付して、申し入れましたが、理事会には対応していただけず、担当事務局からは「オープンしたばかりでとても対応する能力が整っていない。この手のものは3年お待ち願いたい」との回答が寄せられました。
「映像懇」の設置
映像懇は正式には「映像分野の著作権等に係る諸問題に関する懇談会」という長ったらしい名前です。実質的には文化庁長官の私的諮問機関であり、文化庁著作権課が世話役になって、実演家の権利を著作権法上にどう位置づけるかを討議するために97年11月に設置されました。座長は青山学院大学の半田正夫教授(現・学長)で、構成メンバーは日本映画製作者連盟(映連)、日本映像ソフト協会、全日本テレビ番組製作社連盟(ATP)、日本民間放送連盟(民放連)らの製作者の代表、それに芸団協、日俳連、日本映画監督協会、日本映画撮影監督協会(映画カメラマンの協会)、学者、弁護士、映画評論家、俳優代表など総勢23人で構成されています。日俳連からは大林丈史常務理事を代表者として送り込んでいます。また、別に俳優の代表としては森光子氏(現・日俳連副理事長)を送り込みましたが、超多忙でおられる関係で、会議には森氏が出席できない場合の代理として有馬稲子氏、香川京子氏、八千草薫氏、三橋達也氏、佐藤允氏らが出席しました。
映像懇は関係各界から代表的な方々が参加していますが、映連の会長、映像ソフト協会会長らの出席だと話が大局的になりすぎて、具体的提案が難しくなってしまうという側面が出てきてしまいます。そのうえ、実演家の権利が著作権法上でどう条文化されるか、国際条約でどう具体化するのかは極めて事務的な問題でもあります。また、実演家の権利と映画監督のような著作権者の話を切り離して討議しなければならない場面も出てきました。そこで文化庁はこの懇談会の下部組織として二つの「映像懇ワーキンググループ」を設置しました。すなわち、「著作者の権利グループ」と「実演家の権利グループ」です。
日俳連は、当然、実演家の権利グループに属し、このグループには古川事務局長がメンバーとして参画しました。